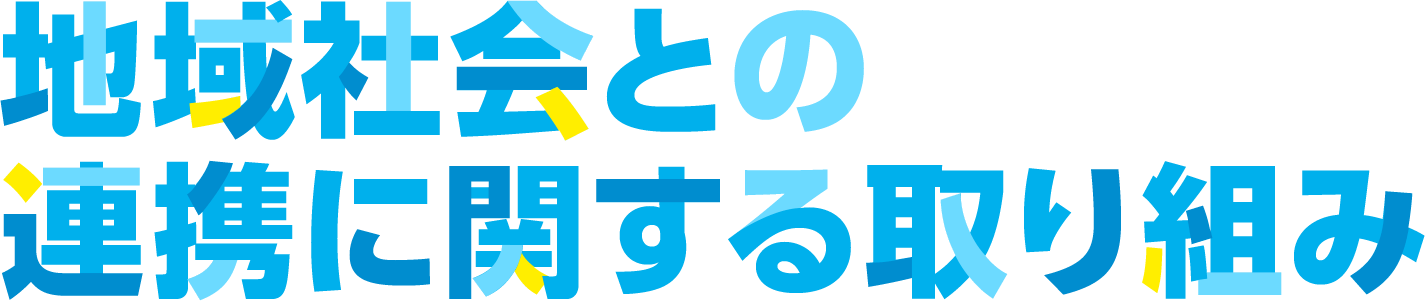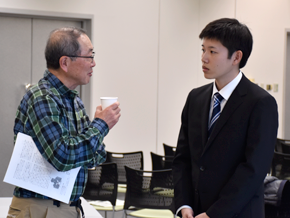活動報告
「第16回地域連携調査研究発表会」を開催 ~都筑区の課題に対し学生らが解決図る~

2019年2月27日(水)、横浜市都筑区総合庁舎にて、「第16回地域連携調査研究発表会」が開催され、本学環境学部・メディア情報学部の学生が卒業研究等で取り組んだ研究について発表しました。当日は、都筑区役所や地域住民の方々が集まり、熱心に耳を傾けてくださいました。
当日は、中野創都筑区長、本学・関良明メディア情報学部長による挨拶、都筑区区政推進課・松本善孝氏による「本学と都筑区役所の平成30年度の主な連携事例紹介」後、学生の発表に移りました。
まず、メディア情報学部社会メディア学科1年生から、テーマ「若者の政治参加と啓発活動」と題し、都筑区と学生グループとの協働によって行われている、学内や都筑区民まつりでの若者政治啓発のためのさまざまな取り組みが紹介されました。
その後、卒業研究報告として、テーマ「シニアの歩行負荷を考慮した避難所へのアクセシビリティに関する一考察」(発表者:環境学部環境創生学科 4年)では、都筑区の防災拠点(避難所)について、防災拠点までの実際の距離ではなく、坂や階段など、シニアの歩行負荷を考慮したアクセシビリティと都筑区の課題について報告されました。
続いて、テーマ「緑地環境における利用者の利用頻度と意識構造の関係性に関する基礎的研究 - 港北ニュータウン・グリーンマトリックスを対象として -」(発表者:同上)では、港北ニュータウンの「グリーンマトリックスシステム」と名付けられた緑道などのオープンスペースの利用頻度や利用目的についてアンケート調査の上、都筑区住民と都筑区以外の住民では公園に求めているものが異なることを指摘、公園管理者は人々の多様な要望を理解し、公園整備を行う必要があると提案されました。
テーマ「ケヤキ街路樹における根上がりの立地・生育環境に関する研究 -あざみ野・たまプラーザ周辺を対象として-」(発表者:同上)では、あざみ野・たまプラーザ周辺の街路樹のケヤキの根上がり(根の生長にともなう植樹枡周囲の縁石の移動、歩道舗装面への亀裂・盛り上がり等)の状況と植樹枡や建物等工作物や傾斜・標高等自然環境との関係について調査の上、植樹枡の縁石までの距離や工作物が根上がりの被害に大きく影響していることが指摘されました。
そして、「都市緑地の管理効果に対する生態学的定量評価手法の開発」(大学院 環境情報学研究科環境情報学専攻 修士課程1年)では、雑木林において常緑樹の伐採や下草刈りという伝統的な里山管理を行い、行った空間と行わなかった空間でギフチョウの繁殖状態を比較するという、生物多様性の定量評価手法の開発に関する報告が行われました。また、発表学生は、こうした評価手法を、都市緑地管理における環境保全評価にも活用したいと考えています。
テーマ「横浜市都筑区の地下水の硝酸汚染の時空的な特性」(環境学部環境創生学科 4年)では、都筑区の災害用井戸42地点について、2018年5月から12月の8ヶ月間、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の数値のモニタリング調査を行いました。その結果、一部に硝酸汚染が深刻な地点もあり、窒素肥料由来の硝酸イオン汚染を防止していく必要があることが明らかにされました。
最後に、テーマ「都筑リビングラボのデザイン」(メディア情報学部社会メディア学科)では、学生3名による、発達障害等の精神的障がいをもつ当事者、NPO法人、横浜市役所、小池研究室が主体となって、当事者の社会活躍を目指していく「都筑リビングラボ」についての発表がありました。そして「都筑リビングラボ」に多様なステークホルダーが参加することでそれぞれの立場を超える「越境」による学びが生じ、全ての参加者に何らかの気づきが生じることや、行政やNPO法人と当事者のみでは支援する側とされる側になるところ、学生が参加することで三角形の関係性ができあがるという、学生の役割について言及されました。
それぞれの発表後には、会場から、都筑区の現状や生活者の視点、行政の専門家としての知識を踏まえた指摘や質問、感想が多く寄せられ、学生は、それぞれの研究が都筑区の問題解決に直結していることを肌で感じることができました。
そして吉田隆彦都筑副区長からの講評、関良明メディア情報学部長からの感想があり、発表会を終えました。その後交流会が開かれ、研究内容についてリラックスした雰囲気の中、来場者と意見交換が行われました。