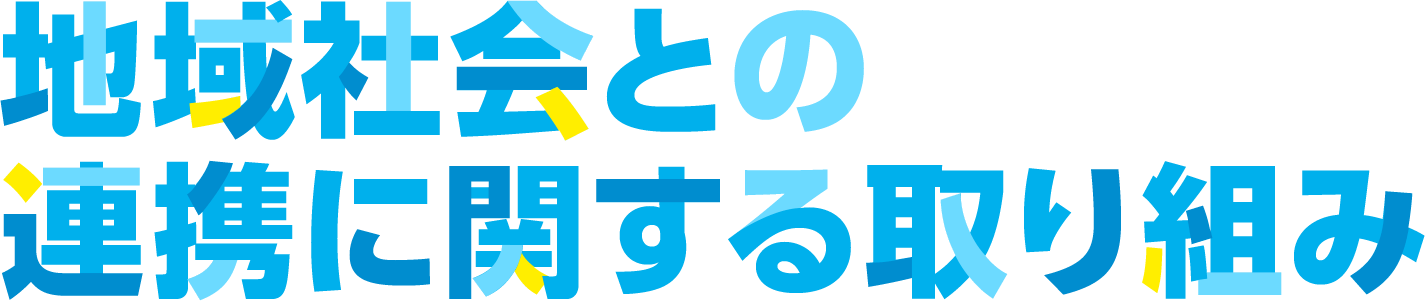活動報告
おやまちシンポジウム「あなたがいるからまちが元気に〜まちとじぶんの新しい関係を探して〜」を開催

2019年2月23日(土)、本学世田谷キャンパスにて、おやまちプロジェクト主催による、おやまちシンポジウム「あなたがいるからまちが元気に〜まちとじぶんの新しい関係を探して〜」が開催されました。
会場には、ハッピーロード尾山台商店街の方々、尾山台小学校関係者、本学都市生活学部の教員や学生、 “おやまちエリア”以外の地域を含め、まちづくりに取り組む団体や自治体などから約80名が集まり、様々な立場の人たちが垣根を超えて未来のまちづくりを考えました。
●オープニング〜おやまちプロジェクト紹介
シンポジウムは、おやまちプロジェクト発起人のひとり、尾山台小学校校長の渡部理枝先生の挨拶に始まり、同じく発起人のひとり、尾山台商栄会商店街振興組合理事の高野雄太さんから、おやまちプロジェクト設立の経緯や、「おやまちデザインプロジェクト」、「おやまちサロン」、「つながるホコ天プロジェクト」など、これまでの活動が紹介されました。
●インプットトーク
その後、「インプットトーク」として、4人のスペシャリストから、まちの未来を考えるヒントとなるような理論や事例が紹介されました。
まず、文部科学省初等中等教育局教育課程教科調査官の長田徹氏から、「地域でつくるキャリア教育の未来」をテーマに、地域の中で子どもたちを育て、さまざまな仕事や大人が働く様子を見ることがキャリア形成につながること、子どもたちが地域社会の役に立つ活動をして有用感をもつことで自己肯定感が醸成されることが、大阪府の小学校の事例などをもとに語られました。
二人目の建築ライターの馬場未織氏は、現在、平日は九品仏、休日は南房総の里山に住む生活を送っています。今回は「まちに関わることでまちも自分も元気になる」をテーマに、まちに働きかけるのではなくまず自分が変わることが大切であること。何か活動をするうちに人の輪ができることが結果としてまちづくりにつながること。過去や社会的地位のレベルアップを目指すのとは無縁の場所であることが大切だということ。そして住民、大学生、旅行者など、異なる立場の人々が一緒に何かをすることで、まちの魅力が再発見できることなどが紹介されました。
三人目の登壇者は、東急電鉄株式会社執行役員・都市創造本部運営事業部長の東浦亮典氏です。東浦氏からは、まず、尾山台の駅勢圏や東急沿線の魅力、東急電鉄のまちづくりの歴史などについて紹介されました。その後、これからは宅地開発と通勤電車、ターミナル駅の商業施設という日本の街づくりモデルが成立しなくなることが述べられ、 “創造経済”の時代を迎えた今、東急電鉄が考える、沿線のまちづくりの構想が披露されました。
最後に、NPO法人ミラツク研究員の森雅貴氏から、リビングラボについて発表がありました。リビングラボは、企業、市民、大学、行政が協力して、実験的取り組みを含め、地域テーマの実現を目指すシステムです。今回は、フィンランドの首都ヘルシンキのカルサタマ地区で電気自動車のシェアやごみの真空収集システムが実現した事例、台湾の台北のある地区では住民が路地に勝手に木を植えていましたが、これをリビングラボの団体がサポートして行政に認めてもらい、ここからコミュニティがさらに活性化していった事例が紹介されました。
●パネルディスカッション
休憩をはさみ、本学の坂倉杏介准教授の司会によって、インプットトーク4人の登壇者によるパネルディスカッションが行われました。長田氏からは、現在の尾山台小学校は日本一キャリア教育がしっかりしている学校であること。馬場氏からは、九品仏の公園で一緒にカエルやセミを観察する仲間ができ、そうしたつながりが生活を豊かにすること。東浦氏からは、東京都市大学の学生と尾山台の街のタッチポイントは意外と少なく、ここにまちを盛り上げる可能性があるのではないかということ。森氏からは、おやまちプロジェクトで出たアイデアを話だけで終わらせず、実験できる場があると良いのではないかという発言がありました。
●「おやまちの未来を描くワークショップ」
慶應義塾大学教授の神武直彦先生がファシリテーターを務めたワークショップでは、参加者全員で、テーブルごとに「10年後の尾山台で起きていたらよいコト」と、「それに向けてどう関わっていきたいか」を話し合いました。
まず、アイデアをブレーンストーミングしながら付箋にどんどん書いていき、それらをインパクトの大小、実現可能性の大小の2軸で模造紙に貼って構造化しました。付箋には、「小中学生が起業」「子どもがいろいろなところで宿題をしている」「まちに屋外キッチンがある」「都市大の学生が商店街で人力車を曳く」など、さまざまなアイデアが書かれ、斬新な発想に会場から感嘆の声が上がる場面もありました。そして最後に、ひとりずつ「自分が街と関わり合いたいこと」を発表し、ワークショップを終えました。
シンポジウムを通し、参加者が“おやまち”、それ以外のまちを問わず、当事者意識をもって、自分が住むまちについて考える時間となりました。