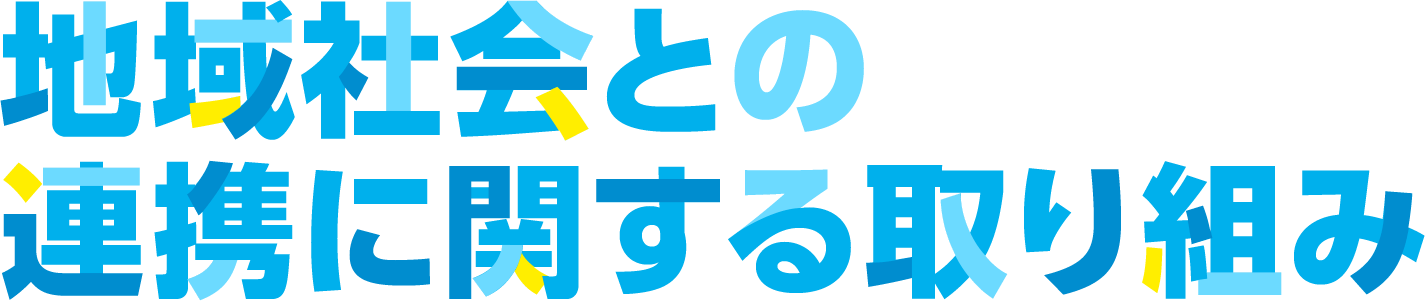活動報告
第3回「軍艦島をはかる」講演会が行われました

2018年3月24日(土)、明治日本の産業革命を支えた世界文化遺産である「軍艦島(長崎県端島)」をテーマとした講演会が、本学二子玉川夢キャンパスにて行われました。この講演会は、東京都市大学と校友会が主催、満席となった会場では、一般の方々や本学教職員・卒業生・在学生などの聴講者が熱心に耳を傾けました。
最終回となる第3回は、「日給住宅(16号棟~20号棟連結建物)をはかる」をテーマとし、岩山の斜面から這い出すように海側の大防潮廊下で連結した16号棟~20号棟に焦点をあて、多くの鉱員とその家族が暮らした鉄筋コンクリート造の集合住宅について、構造と現在の状況、また当時の暮らしぶりなどを2名の講師が講演しました。
第一部と第三部では、本学・濱本卓司名誉教授が「軍艦島をはかる~日給住宅をはかる~」というテーマで登壇。濱本名誉教授は、1974年の閉山以来無人島となった軍艦島の建物群の崩れゆく姿を視覚・聴覚・触覚を用いて、長期モニタリングを行ってきました。第一部では、ドローンによる現在の建物の様子や、複雑な連結からなる建物の図面などの多くの資料映像とともに建築の観点から日給住宅の劣化の様子が語られました。第三部では、これまで取り組んできた視聴触統合モニタリング手法について解説。島内のさまざまな場所に置いたセンサからの情報を、世田谷のキャンパスに居ながらにしてモニタリングして得た情報を島の建造物の保存にいかに生かすのか、軍艦島をはかり続ける意味について語られました。また、これからの社会では都市の老朽化・スラム化・廃墟化が大きな問題となり、今後も建物の長寿命化や、有事への備えなどへ、建築の立場から取り組んでいきたいと抱負を述べました。
第二部では、1947年に家族で軍艦島(端島)に渡り、小学3年生から中学1年までをすごした経験を持ち、元NPO法人軍艦島を世界遺産にする会理事として尽力してこられた、本学工学部建築学科卒業生の中村陽一氏が登壇。大正時代初期に建設された日給住宅について、当時の貴重な資料や体験をもとに講演しました。講演では、在りし日の高層アパートでの豊かで活気あふれる暮らしぶりの様子が語られました。また、劣化の激しい現状と、今後の保存のあり方についての提案があり、多くの課題を浮き彫りにさせる有意義な講演会となりました。
最後に本学建築学科 天野克也教授による「3回にわたった貴重な講演会も今回が最終回となりますが、今後、また研究成果がまとまった折に再度開催してほしいと考えています」との挨拶で4時間にわたった講演会は幕を閉じました。
-
本学・濱本卓司名誉教授による講演の様子

-
中村陽一氏による講演の様子

-
プロモーションムービーの視聴