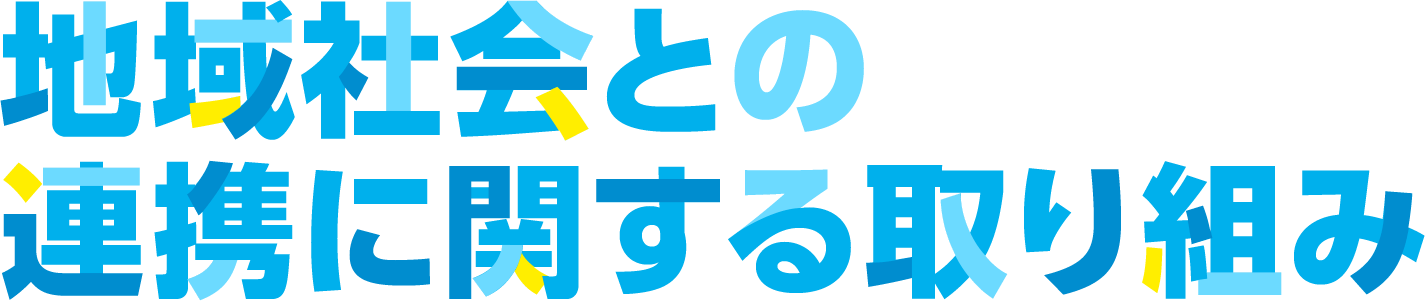活動報告
対話型講座 第5回 「私たちが描く未来の環境都市」を開催しました

11月18日(金)、本学・二子玉川夢キャンパスにて、対話型講座「私たちが描く未来の環境都市」が開催されました。全6回の講座もいよいよ第5回、今回のテーマは「まちづくりの各セクターの役割」ということで、さまざまなセクターを代表する方が登壇されました。
福田紀彦川崎市市長の講演は、市政100周年の2024年に向けて掲げられている川崎市ブランドメッセージ「Colors, Future! いろいろって、未来。」の紹介から始まりました。
川崎市では、東急グループと連携し、空き家対策や高架対策を行ったり、株式会社メガロスとパラアスリートの支援をしたり、川崎フロンターレとサッカー場の整備をしたりと、企業とのさまざまな連携をおこなっているそうです。また、NPOなど多様な主体と連携し、新しい価値を生み出し、新しいアクションを起こしていこうとしている、川崎市の姿勢が力強く紹介されました。
続いて、澤田伸渋谷区副区長は、まず「ちがいを ちからに 変える街。渋谷区」として、7つのヴィジョンを示しました。
セクター横断の仕組み作りに力を入れ、ソーシャルメディアの活用など、デジタル社会の双方向型パブリックリレーションズを推進し、情報戦略を変化させることでさらなる発展をめざす新しい動きは、最先端を行く渋谷区ならではなのかもしれません。
行政のお二人に続いて企業からは、大和リース株式会社の取締役常務執行委員の浮穴浩一氏が登壇しました。企業としてのまちづくりの役割を、官とのパートナーシップを大切にしつつ、官にできないことを行うとし、企業ならではの姿勢が明確化されていました。具体的な例を挙げながら、全国に140カ所ある商業施設を、行政による財政負担を活用しつつ活性化していくというプランは、これからの日本に必要とされている形ではないでしょうか。
本学の枝廣淳子環境学部教授による、「幸せ」という観点からの講演は、原発立地に揺れる柏崎など、実際に現地でまちづくりに携わった経験をもとに、さまざまなセクターとどうまちづくりに取り組んでいくか、具体例を盛り込んだものでした。
その後、「共創の関係づくり」をテーマに、本学環境学部の室田昌子教授がコーディネーターを務める中、4名によるディスカッションがおこなわれました。異なるセクターならではのさまざまな意見が交わされ、まちづくりへの議論が深まりました。さらに、聴衆からも熱心な質問が飛び出し、これまでの連続講座の中でも対話型と呼ぶにふさわしい内容となり、連続講座とすることで講座そのものも進歩してきたようです。
次回はいよいよ最終回となります。本学の三木千壽学長も交え、たっぷり3時間「幸せな未来の環境都市」について議論を深めてまいる予定です。
-
本学環境学部 室田 昌子教授

-
川崎市市長 福田 紀彦氏

-
渋谷区副区長 澤田 伸氏

-
大和リース株式会社 浮穴 浩一氏

-
本学環境学部 枝廣 淳子教授

-
パネルディスカッション・質疑応答の様子