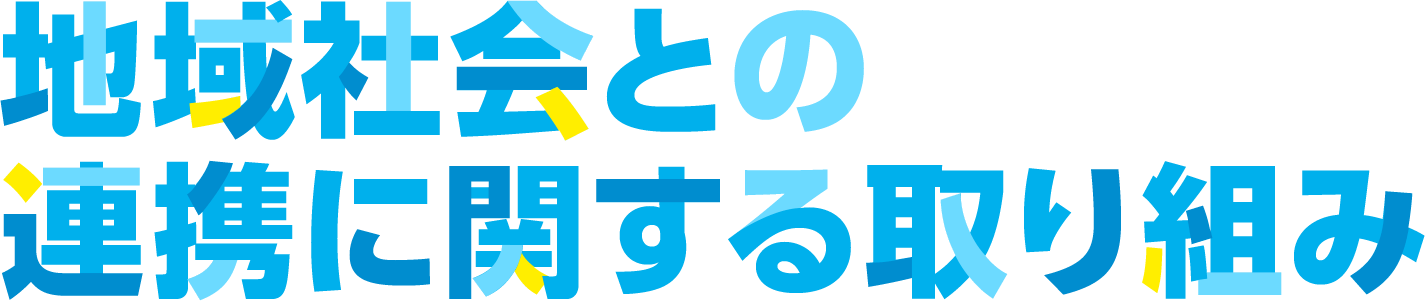活動報告
「東京都市大学・学生による提案と研究の発表会 学生たちと考える自由が丘のまちづくり2019」を開催しました

2019年2月18日(月)、目黒区自由が丘の自由が丘会館にて、東京都市大学と都市再生推進法人ジェイ・スピリット主催による「東京都市大学・学生による提案と研究の発表会 学生たちと考える自由が丘のまちづくり」が開催されました。
当日は、地元住民の方々、自由が丘商店街振興組合や沿線の東京急行電鉄株式会社の方々の来場を得て、都市生活学部学生による自由が丘をフィールドにしたまちづくりについての発表と、質疑応答が行われました。
第一部は、都市生活学部都市プランニング研究室の末繁雄一専任講師から、2018年11月、自由が丘で行った「子育て世代の回遊行動と街の授乳室との関係」についての社会実験の報告がありました。この実験は自由が丘の街に仮設授乳室を設置して、既存の授乳室を合わせ、授乳室の場所や利用状況、授乳室以外での授乳状況と、回遊行動や消費行動との関連などを分析したものです。実験の結果、チェーン店にはない魅力をもつ個店が多い等の自由が丘の特色を考えると、誰もが使える公共の授乳室のニーズが高いことなどが、報告されました。
続いて、4年生の田村舞さんと井村祐樹さんから、卒業研究の報告がありました。
まず、田村さんが取り組んだのは、「商業市街地における子連れ来街者の入店行動と店舗・施設サービスとの関係」です。自由が丘の店舗において「完全禁煙」「子供用食事持ち込み可」など子連れサービスなど充実しているかを調査し、充実度と子連れ来街者の回遊行動や入店回数との相関を分析しました。この結果、「キッズスペース」「授乳室」「おむつ交換台」の有無が子連れ来街者にとって重要で、これらを優先的に設置すべきエリアが提案されました。
井村さんは、自由が丘地区を事例にした「商業市街地の公共空間における飲食物のテイクアウト利用実態に関する研究」について発表しました。調査の結果、自由が丘の街で滞留者が多いのは駅南側の自由が丘九品仏川緑道で、緑道から250mまでがテイクアウト店舗の限界値であることなどが報告されました。そして、駅北側にも滞留空間があれば北側のテイクアウト利用者の増加が見込まれ、店舗の繁栄とともに街に賑わいを生むことができるとの提案がありました。
質疑応答では、授乳室の社会実験については、「授乳室が増えればどこかに遊びに行く際の街の選択率が上がるかどうかを知りたい」、子連れ来街者については、「二子玉川や中目黒など東急沿線の他の街や、沿線以外の街と比較した自由が丘の特徴もわかると良い」、公共空間とテイクアウトについては、「大井町線の線路を越えるという時間距離の勘案も必要」、「季節を変えた調査もあると良かった」といった指摘や感想がありました。
第二部は、3年生3チームによる、「自由が丘のアーバンランドスケープとブランディング」をテーマにした研究発表が行われました。自由が丘には現在、2つの都市計画道路や東急大井町線地下化の構想があります。そこで各チームは、計画によって新たな公共空間が生まれると仮定し、その空間の活用法と自由が丘地区のあるべき将来像について提案しました。
まず「自由が丘総発電」チームは、人が歩くとその振動で発電する「発電床」を都市計画道路や大井町線跡地の歩道に敷き、さらに大井町線跡地には利用すると発電できる健康器具や公園遊具を置く提案をしました。住民や来街者は歩くなどした分のポイントが貯まって地域通貨として使えたり、携帯電話の充電に使ったりできるようにし、街を活性化します。そして電力は街灯など街の電力源とするほか、地域住民や店舗に販売、余剰電力は電力会社に販売するというビジネスモデルです。
「女性が快適に過ごせる街」チームは、大井町線跡地に所属・時間・場所にとらわれない新しい働き方をする女性のためのオフィススペース、コミュニティースペース、一人暮らし用居住スペースをもつビルを建てる、都市開発道路に自由に使えるワーキングスペースや託児所、快適なレストルームを設置、歩道にインスタ映えするカトレアを飾って若い女性に人気のテナントを誘致するといった提案がありました。
「Take Tok」チームは、「テイクアウト文化で活性化!?」をテーマに発表しました。現在、自由が丘でテイクアウトされた商品が飲食されるのは緑道にほぼ限られていますが、大井町線跡地に飲食物持ち込み可能な図書館を開設したり、都市計画道路の両サイドにゆったり過ごせる公共スペースを設置したりすることで、飲食店内の座席数を実質4倍にして街を活性化させるという提案です。同時に、飲料のテイクアウト時マイカップ利用で割引、スマホ決済の導入、テイクアウト商品の売上げの一部を公共スペースの維持管理費に充てる、というビジネスモデルが提案されました。
質疑応答では、会場からビジネスモデルの甘さや法令との不整合など現実的な指摘がなされて学生にとっては勉強になるいっぽう、来場者は、社会人にはない自由で大胆な発想に刺激を受け、自由が丘の将来の可能性を共有する機会となりました。