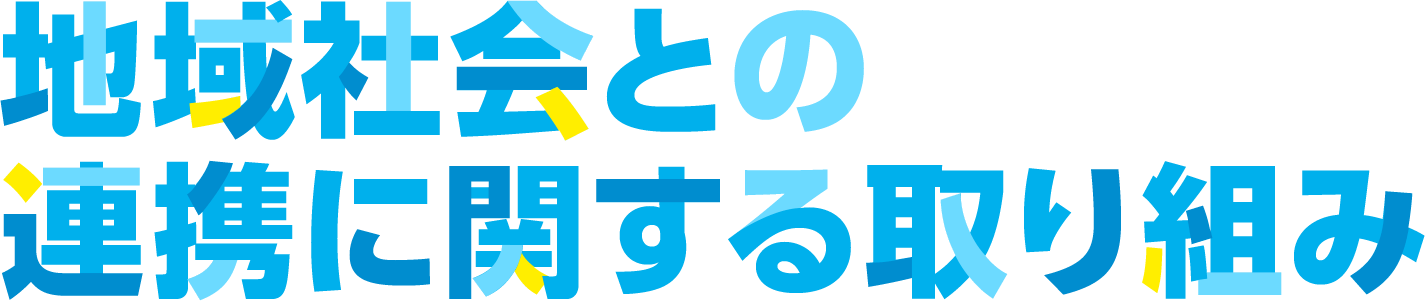活動報告
身近なモノで科学実験!尾山台小学校の子どもたちを招き、ワークショップを行いました

8月27日(月)、本学二子玉川夢キャンパスにおいて、世田谷区立尾山台小学校の児童を招いてのワークショップが開催されました。尾山台小学校と本学、そしてハッピーロード尾山台商店街の地域住民の方々と共同で企画しているこのイベントも4年目となり、参加を希望する児童の数も増加。抽選で選ばれた約60名の児童が、「科学基地においでよ いつもの材料がビックリ変身 大作戦!!」と題された3つの実験に取り組みました。
☆コンクリートのペン立て
最初に取り組んだのは、コンクリートを使ったペン立て作りです。プラスティックのコップの中に粉末状のセメントと水を入れ、よくかき混ぜることで生コンクリートを作ります。その中に一回り小さいコップを押し込むことで、コップ型に生コンクリートを成型。「みんなが帰る頃にはちゃんと固まって、ペン立てになっているんだよ」という大学生の説明に、子供たちは「本当?」と怪訝そうです。中にはコップの縁に触れて「もう固まり始めてる!」と声を上げる子どもも。まさに液体から固体への「変身」に触れる経験になりました。
☆炭でんち
昔から燃やすことで私たちの熱源となってきた木炭を使って、電池を作ります。木炭の片側を食塩水に浸してアルミホイルで包むことで、酸素を吸着しやすい木炭の性質と、酸素がアルミニウムと結合する際に発生するエネルギーを利用するのですが、それによってオルゴールが鳴ったり、プロペラが回ることに子どもたちはビックリ。当初の予定はここまでだったのですが、「電池を全部つなげたら。もっとプロペラが速く回るんじゃない? やってみようよ!」「この電池の電力はどれくらいなの?」といった意見や疑問が子どもたちから出され、電圧計などを用意して実際に試してみることになりました。
☆そらとぶハリがね
磁界の力を活用して、エナメル線で作った円形のコイルを回転させる実験です。コイルの高さや電池との距離など、ここまでの実験よりも気を配らなければいけない要素も多く、子どもたちも四苦八苦。先生や学生たちに相談する場面が多く見られました。調整を重ね、苦労の末にコイルが回ったときには大喜び。さっき作った木炭の電池とつなげて回転するかどうかを試す子どももいるなど、独自の応用を考える様子も見られました。
実験終了後、子どもたちから「家にある身近なモノでも、化学反応を起こしていろいろなことができるんだと分かりました」、「たくさんの実験を、皆と協力して行うことができた楽しかった」といった感想が発表されました。そして工学部の栗原哲彦准教授からは「いま化学反応という言葉が出ましたが、コンクリートが固まることも化学反応です。皆さんがこれから理科や算数を勉強していくと、今日の実験の内容がもっと分かるようになります。ぜひ、今日感じた疑問や面白さを忘れないで、これからの勉強に生かしてほしいと思います」と子どもたちにメッセージが送られ、ワークショップは無事終了しました。
終了後には、実験で作った木炭の電池やコイルのモーターをお土産にもらった子どもたち。もちろん最初に作ったコンクリートのペン立ても、一人ひとりに渡されました。2時間ほど前には液状だったものが乾燥して固まっていることに、子どもたちは驚きを隠せない様子です。帰宅後にはこれらのものを使って、新たな実験を始める子どももいるのではないでしょうか。尾山台小学校や商店街との連携で行っているこのワークショップも4年目を迎え、子どもたちにとって夏の終わりの行事として定着してきました。この取組をきっかけに、一人でも多くの子どもが科学の世界に興味を持つことを願っています。
【サポート役として、貴重な経験を積んだ学生たち】
このワークショップには、子どもたちに実験を指導する役として、約20名の東京都市大学の学生たちが参加しました。児童教育の実践や自身の研究テーマの振り返りなど、学生たちにとっても大きなプラスとなる体験でした。
人間科学部児童学科 2年 榎本文香さん
児童教育について学んでおり、今回初めて参加しました。小学生と接するのは初めてだったのですが、彼らの意欲的な姿勢にまず驚かされ、教える際にはかみ砕いて分かりやすく指導することに留意しました。一方で、彼らの疑問に即答することもできたのですが、どこまで教えればいいのかといった「さじ加減」については少し悩みました。そうしたことを、これからの勉強で学んでいきたいと思っています。
工学部都市工学科 4年 吉田拓矢さん
コンクリートに関する研究室に所属しています。今日の実験でもコンクリートでコップを作りましたが、生コンクリートの特性など、自分では十分理解していることもきちんと説明することが大事なんだと分かり、いい振り返りになりました。この実験をきっかけに、より深い部分まで興味を持ってもらえたらいいなと思います。また児童学科の学生は子どもたちの扱いに慣れていて、そういう部分でも勉強になりました。
-
会場の様子

-
コンクリートのペン立て作り

-
炭でんちの実験

-
学生も参加者も真剣そのもの

-
そらとぶハリがねの実験

-
コンクリートのペン立ては持ち帰りました