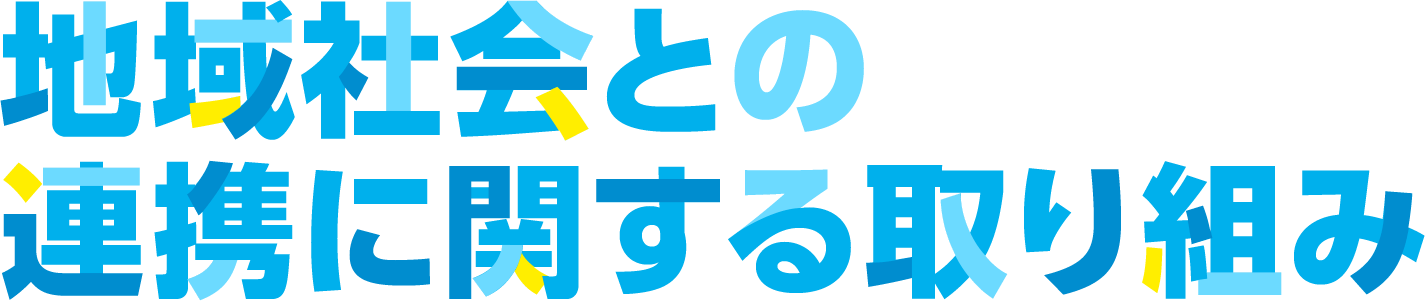活動報告
第二回「軍艦島をはかる」講演会が行われました

2017年9月30日(土)、明治日本の産業革命を支えた世界文化遺産である「軍艦島」をテーマとした講演会が、3月に開催された第一回に続き本学二子玉川夢キャンパスにて行われました。この講演会は、東京都市大学と校友会によって開催され、一般の方や本学教職員、本学学生、本学卒業生などの熱心な聴講者で会場は満席となりました。
第二回となった今回のテーマは、「小中学校(70号棟)、耐波建築(31号棟)、最大の建物(65号棟)をはかる」というもの。軍艦島建築群の中から、子どもたちの小中学校として使われた70号棟、島内を台風や時化による大波から守るために造られた31号棟、島内最大規模の鉱員アパート65号棟の今と当時の思い出について2名の講師が登壇しました。
第一部は、本学名誉教授の濱本卓司教授が「軍艦島のいまをはかる」というテーマで多くの資料映像をもとに講演。濱本教授は1974年の閉山以来無人島となった長崎県端島(軍艦島)の崩れゆく姿を、視聴触統合モニタリングという視覚・聴覚・触覚を用いた手法で、長期モニタリング調査を行っています。今回は70号棟、31号棟、65号棟に焦点をあて、その建造物の構造と劣化の現状について解説しました。
モニタリングには太陽光パネルによる電力を使用し、各所に配置した振動センサによって触覚的にその崩壊具合を調査。ドローンやウェブアラブルカメラによる外部・内部の映像も利用しています。島内でも比較的新しい70号棟の調査では、7階の鉄骨造の増築部分がほとんど倒壊しているのに比べ、鉄筋コンクリート構造の6階までは劣化が少なく、廊下部分ではほとんど傾きがないという調査結果から、ラーメン構造がいかに強いかが説明されました。また、護岸が決壊した結果、建物の基礎部分がごっそり削られ宙に浮いている状態であるということでした。また、コの字型をした巨大なアパートである65号棟、防潮棟として海側に開口部を小さくし、棟屋内を石炭殻(ボタ)を捨てるためのベルトコンベヤが貫通した特徴ある造りの31号棟についても、その構造と劣化の様子が語られました。
第二部は、元NPO法人軍艦島を世界遺産にする会理事で、本学工学部建築学科卒業の中村陽一氏によって、軍艦島の当時の人々の暮らしを氏の貴重な体験と現在の資料映像とともに語っていただきました。中村氏は1947年に家族で軍艦島(端島)に渡り、小学3年生から中学1年までをすごした経験を持ち、軍艦島を世界遺産に登録するために尽力してこられた人物です。冒頭に流された産業遺産国際会議で軍艦島をアピールするためにつくられた映像紹介では、思わず涙する聴衆も見受けられました。講演では、報国寮と呼ばれた島内最大にして最多戸数(388戸、RC造10階)を誇った65号棟の華々しい活気ある暮らしぶりについてや、郵便局や理髪店、共同浴場なども併設された31号棟の鉱員社宅について語られました。また、端島小中学校(70号棟)について、今でも残っている子どもたちがつくったモザイクタイルの壁画の映像とともに、子どもたちの楽園であった当時の様子が紹介されました。中村氏は、世界文化遺産となった現在も軍艦島の建物の劣化と倒壊を防ぐための活動に奮闘中です。倒壊を防ぎ次の世代に産業遺産としての軍艦島を語り継ぐための熱意を感じることのできた講演でした。
第三回講演会は「日給住宅(16~20号連結建物)をはかる/軍艦島をはかり続ける意味」と題して、来年3月24日(土)に予定しています。
-
濱本卓司 本学名誉教授による講演の様子

-
中村陽一氏による講演の様子

-
質問タイムの様子