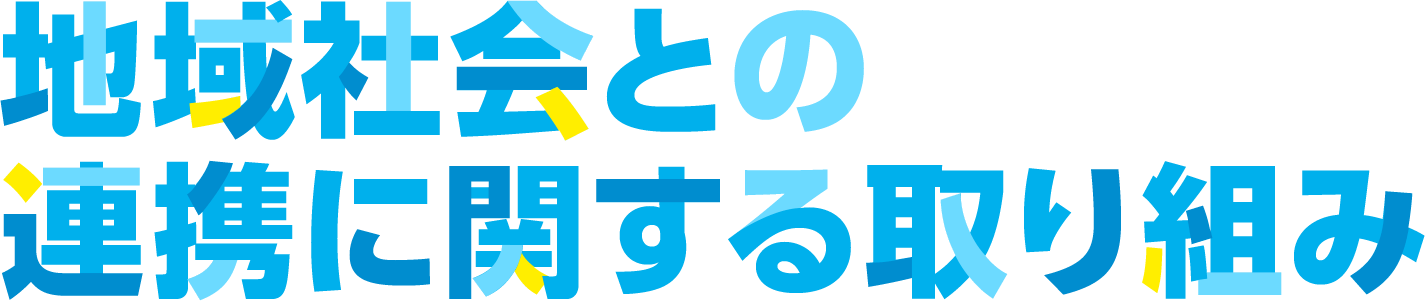活動報告
講演会「伊藤若冲若 動植綵絵の色と描写」を開催しました

11月6日(日)、二子玉川夢キャンパスにおいて、本学主催による講演会「伊藤若冲 動植綵絵の色と描写」を開催しました。講師は、本学の卒業生であり、独立行政法人 国立文化財機構 東京文化財研究所で、伊藤若冲の研究をはじめ、日本絵画材料の変遷や、文化財の非破壊調査法の研究に携わっている早川泰弘氏が務めました。会場には、最近の伊藤若冲ブームを反映してか、老若男女さまざまな方々が足を運んでいました。
講演は、まず伊藤若冲の紹介に始まり、講演のメインテーマとなる作品「動植綵絵」を取り上げました。ただ、早川氏は本学の工学部電気工学科卒業であり、一見日本画とは遠い印象です。そこでこの日は、分析科学という観点から、普段人間の目では見えないところを解説する、興味深い講演となりました。
講演タイトルにもあるように、話の中心となったのは、伊藤若冲が使用した“色”についてです。その“色”を科学的に分析すると、ただ作品を目で見るだけではわからないことが次々と明らかになったのでした。その結果を、白や赤、黄、茶といった色をひとつずつ取り上げ、それがどの作品にどう使用されており、それぞれがどう異なるか、わかりやすく具体的に説明されていきました。
たとえば、一見同じように見える赤でも、材料を調査した結果によれば、4種類の赤があります。「老松白鶏図」と「老松白鳳図」では、同じように右上に太陽が描かれていますが、実はこの赤は、異なる赤で描かれているのだそうです。また、「紅葉小禽図」では、紅葉が描かれている中、たった一枚のもみじの葉だけが表からのみ描かれ、それ以外は全て表と裏から描かれています。
このように、伊藤若冲の絵は、ディティールまで突き詰めてリアルに描かれているだけでなく、非常なまでのこだわりがあることがわかりました。その分析結果を眺めると、ここにこだわろうという強い意志が見られるのだそうです。このように人間の目では認識できないレベルの描写にこだわったのが、伊藤若冲という画家なのです。
また、伊藤若冲の描写については、鶏だけが描かれている「大鶏雄雌図」と「群鶏図」が取り上げられました。これらの両作品は鶏という同じテーマで描いているにも関わらず、「群鶏図」が「大鶏雄雌図」に対して、一見カチッとした印象に見えるのは、有機染料を使わずぼかしを用いていないことから生じるそうです。
最後に、「菜蟲譜」という、伊藤若冲が75歳の晩年の作品を「動植綵絵」と比較し、伊藤若冲のまた異なる魅力が紹介されました。
講演終了後は、聴衆からたくさんの質問が寄せられ、これまでとはまるで異なる観点からの鑑賞法に、伊藤若冲への興味、関心がさらに高まった様子がうかがえました。さまざまな方が集い、新たな知の楽しみを提供できたことは、情報発信基地である同キャンパスとしても、貴重な機会となったと考えております。
-
本学 湯本副学長 ご挨拶
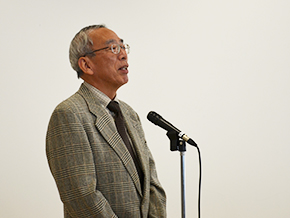
-
講師の早川 泰弘氏

-
講演中の様子

-
質疑応答の様子

-
本学 岡田准教授 総評の様子

-
講演後の展示の様子