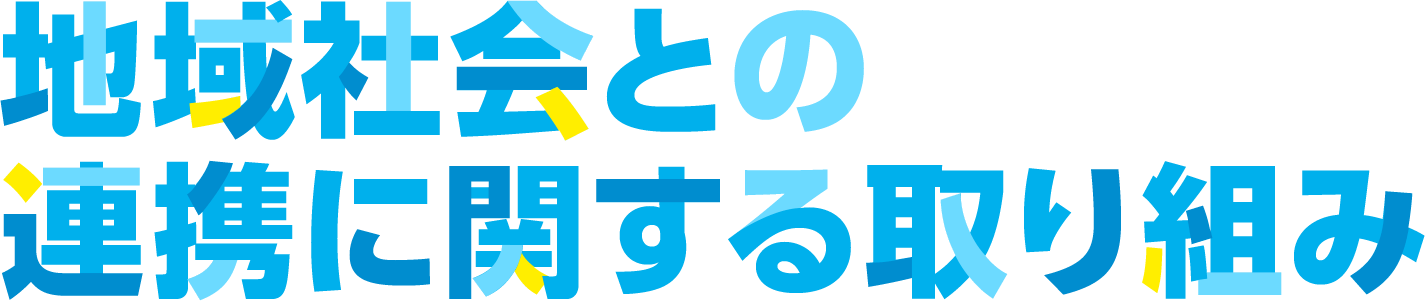活動報告
夢キャンコミュニケーターが「夏を乗り越えよう 3Dペンを使ったミニ紙すきうちわ作り!!」を開催しました(8/31)
2025年8月31日(日)、夢キャンコミュニケーターが世田谷キャンパスにて、「夏を乗り越えよう 3Dペンを使ったミニ紙すきうちわ作り!!」を開催し、親子15組が来場されました。
説明工程では、伝統文化であるうちわに興味を持ってもらうため、参加者に「日本三大うちわ」のひとつである丸亀うちわと土佐和紙の動画を視聴してもらいました。丸亀うちわは一本の竹から作られているという特徴や四国全体で作られる伝統産業であることなどの紹介や「和紙の材料として正しいものは?」(答えは、こうぞ)「丸亀うちわは、1年間でどれくらい作られているでしょうか」(答えは、1億本)といったクイズの出題があり、参加者と夢キャンコミュニケーターの学生たちが一緒に考えました。丸亀うちわの生産量には、参加者から驚きの声があがりました。
制作工程の紙漉き作業では、学生たちが参加者をマンツーマンでサポートしながら、「材料の牛乳パックをちぎる」「ビーカーの水に入れる」「ミキサーでまぜる」「紙すきセットを使って紙をすく」「タオルでじっくり乾かす」の5つの工程で、地紙(じがみ)部分を完成させました。
3Dペンで骨子を作る作業では、材料となるカラフルなフィラメントの中から好きな色を参加者に選んでもらい、骨子が描かれた紙を下敷きにして、3Dペンでうちわの形を作りました。3Dペンの先端は高温なため、学生たちが注意しながら見守り、余分なフィラメントをハサミで切るなど細かい作業をサポートしました。最後に地紙を骨子に貼り、うちわを完成させました。サインペンでイラストを描いたり、おりがみで色とりどりの飾りを作り、個性豊かなうちわが完成しました。
参加した子どもたちからは「3Dペンが楽しかった」「うちわや昔のものにとても興味を持ちました」「牛乳パックの真ん中をむくのが難しかった」といった声がありました。
「うちわがどう作られているのか興味を持ってもらい、自分でモノを作る楽しさや難しさも体験してもらいたいという想いから今回の企画を考えました。創意工夫をもとに、子供達の個々の才能が表れた作品がつくられて良かったです。」と企画と進行を行った寺部陽人さんはイベントを振り返りました。









<関係するリンク先>
・夏を乗り越えよう 3Dペンを使ったミニ紙すきうちわ作り!!
・夢キャンコミュニケーター
・夢キャンコミュニケーター学生ウェブサイト