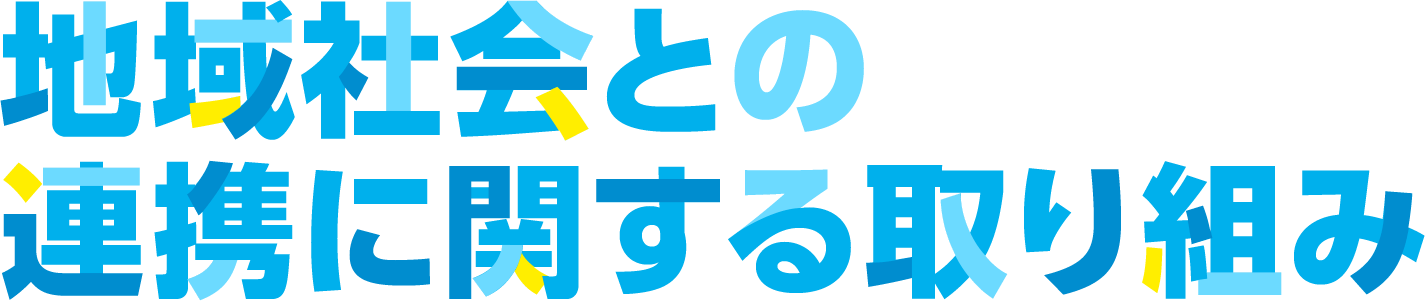活動報告
平成29年度「等々力地区防災塾」に本学共通教育部・岡山理香准教授が参加しました
 講評する共通教育部・岡山理香准教授
講評する共通教育部・岡山理香准教授
2017年11月12日(日)、尾山台中学校にて、等々力地区区民防災会議委員、地域防災リーダー、避難運営委員会構成員、福祉関係事業者、東京都市大学などの関係者が参加し、「等々力地区防災塾」(避難所運営用資機材操作等研修会)が開催されました。この防災塾は平成26年度に世田谷・等々力地区における自然特性および社会特性を踏まえて、住民自治の強化と地域防災力の向上のため「等々力地区防災計画」を作成することを目的として発足。今年度も「発災後72時間は地区の力で乗り切る」をスローガンとして策定した地区防災計画をもとに、より実践的な訓練を実施し、計画の検証を行いました。本学岡山准教授は、世田谷区教育委員会・地域運営学校委員であることから防災計画の策定に参加、引き続き活動を行っています。
避難所運営用資機材操作等研修会として開催された今回の防災塾。第一部は社会福祉法人世田谷ボランティア協会 事務局長 吉原清治氏を講師に迎え「災害ボランティアセンターとマッチングシステムについて」の講義が行われました。講話の中では、「①災害時のボランティアによる支援活動をイメージして、ボランティア受け入れ態勢の必要性を理解する。②世田谷区でのボランティア受け入れ体制とコーディネーターの役割を理解する」の2点が語られ、参加者からは熱心な質問が寄せられました。その後、岡山准教授が登壇し、「これまでの大災害の反省を踏まえて、サテライトでの割り振り、柔軟性をしっかりと考えていかねばならない」と講評しました。
第二部の資機材操作研修会では、消防団や機材の専門家による実地の説明を交え、防災無線、災害時有線電話の操作、炊き出し用バーナーおよび発電機の操作、マンホールトイレ、投光器の現物確認、受水槽・高置水槽の確認、備蓄物品(応急救急セット、リアカー)などの確認が行われ、校庭にて防災食品の試食会をもって、防災塾は終了しました。
参加者からは、それぞれの備品や器具の使い方、注意点などへの質問が相次ぎ、備えへの大切さを再確認できた研修会となりました。
-
吉原清治事務局長による講義

-
リアカーの扱い方確認の様子

-
炊き出し用バーナー操作確認の様子